COLMUN
コラム / IT化経営羅針盤
IT化経営羅針盤252 極論は危険 「パッケージソフトに体を合わせろ」
2025.07.22
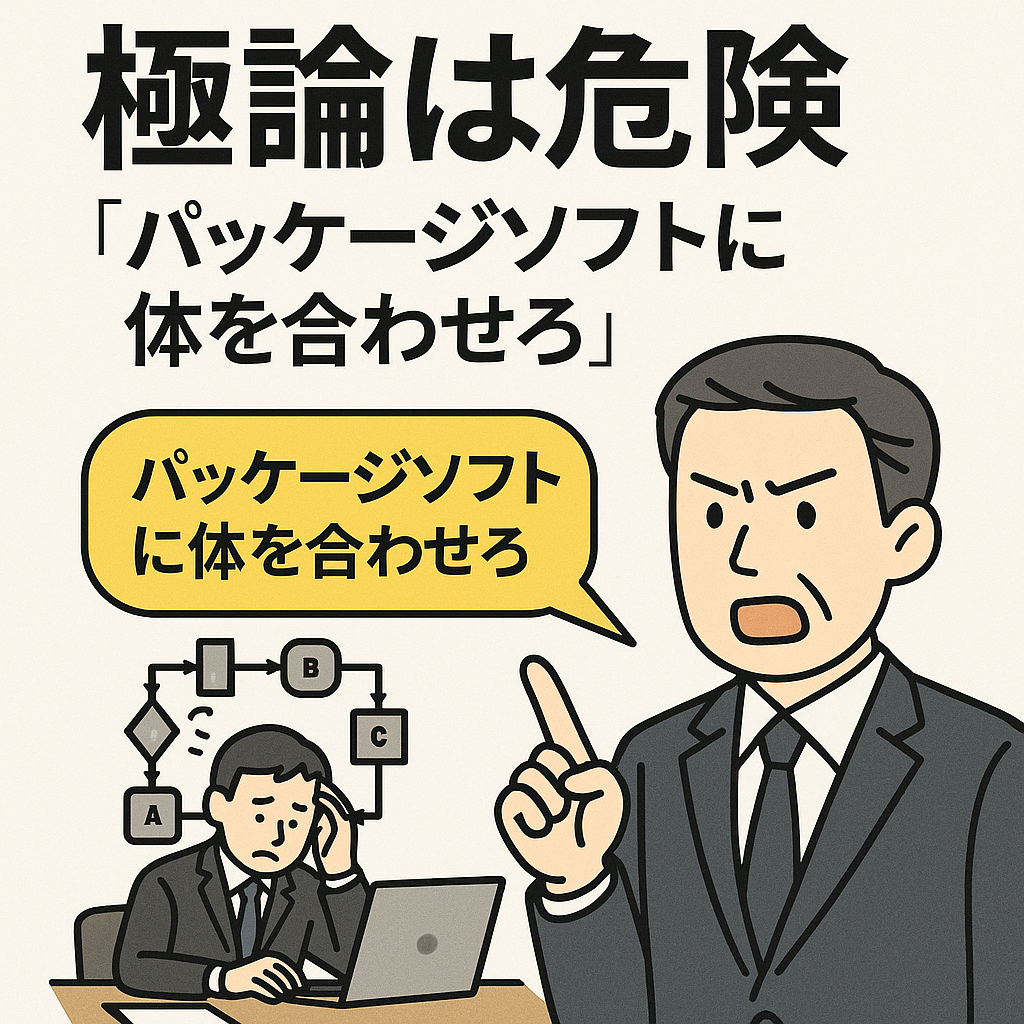
ご相談のあった会社で、またもや聞いたフレーズ。「このシステムを導入する際、業務プロセスはパッケージソフトに合わせることを基本とする」という言葉です。あらかじめ申し上げますが、これは決して間違いではありません。それを否定することも致しません。しかし、大きなリスクを内包していることがあるのです。今回はそのような状況を見極める方法を解説します。
標準業務プロセスが非公開/説明されないケースがある
大手のパッケージメーカーのソフトには、大抵の場合標準業務プロセスの資料があります。広く公開されている場合もあれば、NDAや契約を締結したり、有償教育を受けた場合にのみ開示されるものもあります。
このような資料が開示されていれば、いったん一段落できるのですが、そうでないソフトを選定してしまった場合には、さあ大変。後から標準フローが存在しないことに気がつき、ソフトの機能を一つずつ確認しつつ、どのような業務プロセスになるのか「試行錯誤」が続いてしまうことになります。フローが比較的単純な業務なのであればなんとかなるかもしれません。しかし、例えば生産管理システムなど、業務プロセスが非常に長く複雑化しやすい業務のパッケージソフトは、この試行錯誤のハードルが極端に高くなります。
しかも、このようなソフトを開発・販売している会社の担当者に話を聞くと、「使い慣れていただければ大丈夫です」といった発言も飛び出すことも。確かに、ソフトを設計している立場に立ってみれば、何も資料が無くとも全部頭の中に前提条件が入っているので、目に見える資料など不要であり、それを外れるプロセスが顧客企業のところにあった場合は「合理的では無いプロセスだ」と決めつけてしまいがちです。作る側の論理では無理もないことでしょう。
しかし、そのようなパッケージを選んでしまった側にはとても大きな負担になってしまいます。
一方、標準業務プロセスの資料が公開されている場合でも手放しで安心はできません。なぜならそれを説明するべき人(ソフトメーカーの窓口やSIerのプロマネ)が、うまく説明できないケースもあるからです。これは、ソフトウェアメーカーが業務プロセスのところまで立ち入って顧客をサポートする義務が無い、という根強い意識があるからに他なりません。何回かご説明している通り、
業務プロセスはユーザー企業の責任で組み立てるもの
だからです。これを極端に解釈すれば、「標準業務プロセスの資料は渡すから、あとはユーザー企業側で検討してね」ということとなってしまいます。さらに、その資料も(国際標準だから、という理由で)エンジニア視点で描かれていることが多く、読み慣れないと解読が難しいものです。これを比較的短い期間の中で読み解け、とユーザー企業側担当者に強いるのは、大きな負担になりますし、なかなか簡単にはいきません。 標準業務プロセスを解説した資料が存在するか?それを納得いくまで説明してくれる体制があるか?といった確認を、パッケージソフト採用決定の前にしておかないと、後の段階で担当者が大変になる、ということを忘れてはなりません。
標準業務プロセスの徹底的な把握と分析が超重要
さて、そのような標準業務プロセスが十分に解説されたとしても、「パッケージに体を合わせる」という趣旨で考えると問題も多いものです。社長や経営層はあまり業務プロセスに関心が無いかもしれませんが、その会社特有の社内業務プロセスは、カスタマーサクセスや顧客満足度の視点でとても重要な役割を演じていることが少なくないものなのです。
良く引き合いに出しますが、納期回答は社内業務プロセスに非常に密着に関係しています。製造業であれば、ご注文を受けた後に、製品在庫を引き当てようとするでしょうし、それが無ければ部品在庫を引き当てて製品製造を計画しないことには納期は回答できません。さらに、部品在庫が足りない場合には追加発注をするでしょうし、そうなるとその納期回答が来るまでお客様に確定納期を案内できなくなってしまいます。このような数多くのプロセスを経てお客様に納期回答しているはずですが、それを知っている人は会社内でもごくわずかな担当者たちであり、経営上層部は正確にそれを把握できていないことも多いものです。
にも関わらず、このような責任ある立場の方々が「パッケージを使うのだからその業務プロセスに仕事を合わせよ」と社内号令をかけてしまうのは、いかがなものでしょうか?ともすると、この号令は絶対命令として社内に訓示されてしまい、担当者は不満や課題を抱えながら文句を押し殺して導入作業を始めてしまいます。これではうまく進めることができないばかりか、パッケージ稼働後はその会社の顧客対応はとてもギクシャクしたものになってしまうのは自明の理ですね。
社長・経営層は、「とにかくパッケージに合わせよ」と号令を出すのではなく、
パッケージの標準プロセスをメーカーやSIerに説明してもらい
そのプロセスと自社のプロセスの違いをはっきりさせ
違いが存在する場合はそれを受け入れるのか、それともカスタマイズなどのソフト変更をお願いするのか決断を下す ということをやらなければならないのです。
————————-
ソフトウェアメーカーから顧客企業の社長に「パッケージにやり方を合わせないと効果が出ません」という説明をしているシーンは幾度となく見たことがあります。もはや常套句です。しかし、これは極端すぎる説明ですし、ソフトウェア企業側にはきちんと正しい説明をしていただくように求めたいものです。また、導入する側の社長にも、そのような言葉に対する盲信をしないようにお願いしたいものですね。
無料メール講座登録
経営者様向けのIT化ヒントが詰まった無料メール講座や代表コラム「IT化経営羅針盤」、各種ご案内をお届けします。
資料請求
パンフレット、コンサルに関する資料のご請求は下記フォームからお願いします。
CONTACT
お問い合わせ
(TEL: 050-8892-1040)
