COLMUN
コラム / IT化経営羅針盤
IT化経営羅針盤259 社員が業務改善に取り組めるように仕向ける極意とは?
2025.09.24
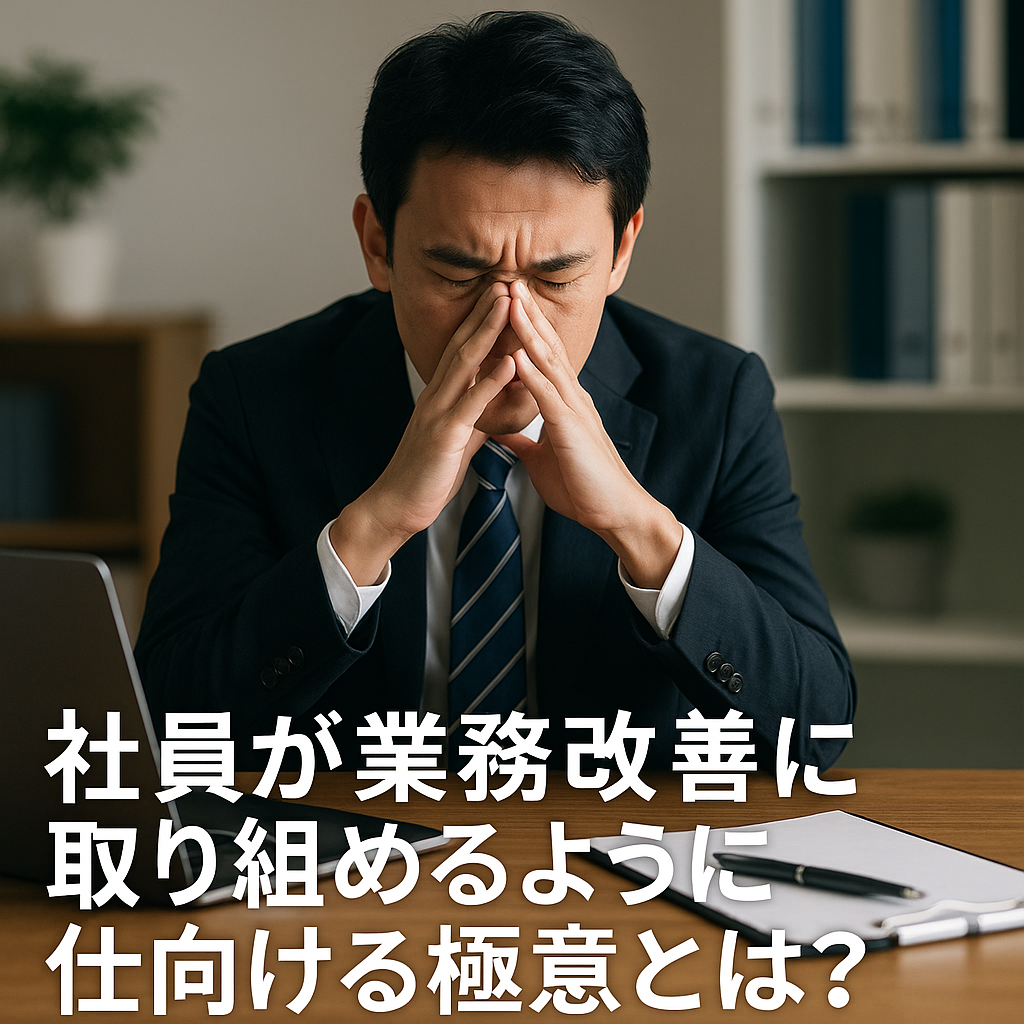
先日、ある新規のお問い合わせを頂いた社長からWEB会議で相談を受けていた時に、ふと社長からのぼやき(失礼)がありました。
「まだまだ仕事を合理化できる部分があるはずですし、それによって社員の仕事が楽になるはずなのに、担当者が忙しがってやってくれないんです。それに、合理化はおおかたやり尽くしたから、今から改めて合理化検討しても効果は期待できませんよ、とも言うのですよ。私としては、まだまだ改善の余地があると思えますし、やめてしまえる仕事もあると思っているだけに、このネガティブな反応はこたえます…。」
確かにこんなことを言われてしまっては、よほどトップダウンが強力な社長でないと説得しきれませんね。しかし、ご安心頂きたいのですが、私の経験では「社員からネガティブな反応をされるのは、どの会社も似たり寄ったり」なのです。今回はその原因系と対応について話を展開します。
- 社員が業務改善に後ろ向きな不都合な理由
- 「鶴の一声」で業務改善する気にさせる極意
社員が業務改善に後ろ向きな不都合な理由
まず原因系ですが、私のコンサルティング経験では以下が考えられます。中にはあまりにも切実で、語るに涙…もあります。あまりにも原因が多いので、その中のトップ5をご紹介しましょう。いろいろな誤解を招きそうですので、敢えて順位は付けません。
<自分たちの仕事がなくなると疑っている>
これは昨今の働き方改革でも顕在化している問題です。「業務改善」というワードを聞いた瞬間に、「自分の仕事がなくなるかもしれない」と警戒する。これは、特に非正規社員に発生しがちです。非正規といえども10年選手の社員が多く働いている会社などでは、これら非正規人材に仕事を任せきっている場合があり、その仕事がある間は安定して働けると信じている人が多いですよね。このような社員が多い現場で、業務改善を叫んだ瞬間に皆さん疑心暗鬼になるのが目に見えます。業務改善できたあかつきには自分たちの職が無くなる…。これは想像に難くないと思います。もっとやっかいなのが、「自分のやり方と同僚のやり方を比較される」と警戒しているパターンです。私も何回もそのような場面に出くわしましたが、同じ仕事を複数のメンバーで垂直に分業している場合、その業務処理手順や方法が人によってマチマチになっており、作業効率に差が出ていることがあります。当然どちらか効率の良いやり方に合わせるように業務改革することが多いわけですが、そうなると効率が悪いと判断された人の仕事がなくなる可能性があり、そのような人たちから多かれ少なかれ抵抗されます。この、「人別に作業効率が異なる」という現象は何かと潜在化してしまって表には出にくいため、ここをほじくり返そうとすると途端に非協力的な態度で固められてしまいます。
<自分は改善を提案してきたが、他の人が協力してくれない>
「業務改善を頑張っても、どうせ今まで通り川下の職場が協力してくれず、立ち消えになるだけだ」という固定概念です。これは、業務プロセスが比較的長い会社で発生しがちです。例えば、川下部門の人たちが、川上部門の人のやっている仕事の理解が足りない、という場合に発生しやすいもので、そのようなことが何回か続くと、社内でも部門間対立になっていたりします。大抵の場合、これも潜在的に隠れているので、「業務改善する」と言った時に陰口のようにネガティブな反響が返ってきて、それも陰湿なことが多いやっかいなものです。
<自分はたいしたことをしていないと思っている>
これはベテラン社員に多いことです。「自分の経験と能力があれば」という前提を全く認識していない社員の場合に思い込みがちで、業務の可視化をお願いしても「これしかやっていません」的に超概要しか説明してくれない、という反応に繋がります。また、「この程度の仕事であれば誰でもできるので、可視化などする必要もない」という反応を見せることもあります。これも自分の能力を棚に上げている発言であることが多く、実際に業務を分解してみると複雑怪奇であることが多いのはご想像の通りです。また、そのような場合、業務可視化のヒアリングをすると、論理的な説明をしてくれないケースも多く、社長や可視化の関係者は非常に苦労させられます。
<何回も業務改善提案したのにそのたびに却下されてきた>
社長がそのような認識を持っていない場合が多いのですが、過去に1回以上現場から改善の提案がなされて(もしくは提案したつもりで)いたにも関わらず、無視されてしまった・後送りされてしまったと(思い込んでいる)ケースです。提案した内容が非常に些細な内容であることも多く、覚えている社長があまりいないということも特徴的です。この場合はかなり根に持っていることもあるので、社長には直接話が来ません。潜在的な抵抗勢力になってしまうこともあり、対応するにやっかいです。
<自分のやっている仕事は最適化されていると思っている>
これも、単なる思い込みの場合が多いのですが、「この仕事は自分なりに色々工夫してきた。これ以上改善のしようもない。だから検討してもムダだし説明の時間さえも惜しい」と敬遠されてしまうパターンです。このような社員はとても優秀な方が多く、手元の仕事の最適化についてはピカイチであることが多いものです。しかし、「全業務プロセスの上での最適化」という発想ではないため、社長から見ると「何をムダなことをしているのか?」と思ってしまうモノが多く、この齟齬が現場の非協力を生んでしまいます。 いかがでしょうか?皆さんの会社にも多かれ少なかれこのような状況にあると思います。
「鶴の一声」で業務改善する気にさせる極意
このような社員が抱えている認識や誤解について、社長が一点一点対応していてはなかなか前に進みません。強力なリーダーシップやトップダウンができる社長であれば、無理矢理にでも業務改善活動に取り組ませるのでしょうけれども、そのようなことをすれば禍根が残りますし、良い成果も生みません。それよりも、業務可視化を経由して改善に導くために社長が起こすべき言動があります。
下準備:例え業務改善の目的が固定費削減であったとしても、特殊な場合を除いて「断じて社員削減を想起させてはいけません」ので、そのための下準備・環境作りが必要となります。会社ごとに事情が異なるので、ここでは断定致しませんが、「業務改善の目的をきちんと説明する」ということに尽きます。
それは、「一人あたりの生産性向上」や「付加価値の高い仕事への配置転換」などであるべきですね。
社長の本気を示す鶴の一声:その下準備を終えた、もしくは、方針や計画を示した上で、業務改善に向けた作業への参加を指示し、社員モチベーションを高める一言は、これに尽きます。
「会社全体で業務プロセスを見直し、抜本的対応を図る」 です。決して、部分改善を匂わせてはいけませんし、中途半端感を出しても反発されるばかりです。ここで「会社全体」がパワーワードであることにご注目頂きたいと思います。よくある間違いが「一人一人の作業を根本的に見直し…」という表現です。これでは活動全体がこじんまりしたものの集合体になりがちですし、社員側も「結局自分たちにだけやれと言っているのだろう」というネガティブな印象を持ってしまいます。もし、基幹システムパッケージを導入する方針なのであれば、パッケージに仕事を合わせる必要が生じますが、その場合は「組織も仕事も設計しなおす」ぐらいの覚悟が必要となります。決して現場任せではできないことですし、そんなことをやってしまうとカスタマイズが肥大化して予算が膨大なものになってしまったり、うまく運用できずに頓挫してしまう失敗のリスクが増えるだけです。その際も同様で「全社の業務を根本的に見直す」という号令が必要なのです。
——————-
冒頭ご紹介した社長も、この「会社全体の業務プロセス見直しを号令するべき」というお話をした際には、少し戸惑っていらっしゃいましたが、まず最初にアウトプットされる「業務プロセス」の可視化結果について、その対策は会社の体力に応じて段階的に計画されるべきものですので、そこまで含めて社員に説明し理解を得ることが重要だとご説明したところ納得されていました。業務改善やそこに至る可視化については、何かと現場に任せがちになりますが、その前提の場合は出てくるアウトプットも効果も粒が小さいものとなり、充分な効果を上げられません。壁は高い様に見えますが、決意の上で全社で取り組む、という姿勢を示すべきであると思います。
無料メール講座登録
経営者様向けのIT化ヒントが詰まった無料メール講座や代表コラム「IT化経営羅針盤」、各種ご案内をお届けします。
資料請求
パンフレット、コンサルに関する資料のご請求は下記フォームからお願いします。
CONTACT
お問い合わせ
(TEL: 050-8892-1040)
